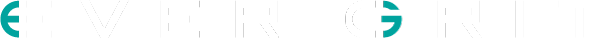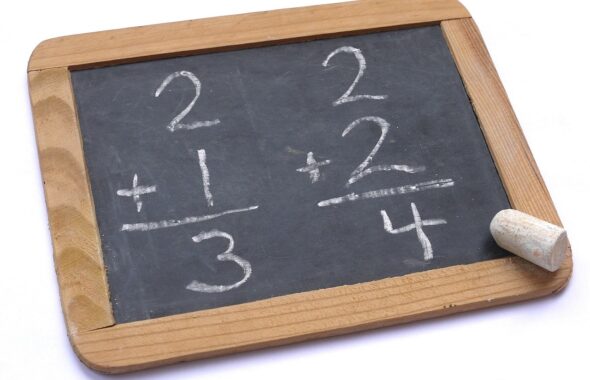節税にならない!?ふるさと納税は何がお得なの?
ふるさと納税とは、2008年の税制改正とともに始まった制度です。
「節税」のイメージが強いと思いますが、実はふるさと納税は税金を減らす制度ではありません。では、なぜお得だと言われるのでしょうか。
今回は、ふるさと納税について解説していきたいと思います。
1.ふるさと納税は故郷への「寄附」 制度誕生の背景としくみ
仕組みを理解するために、まずは制度が誕生した理由を見てみましょう。
多くの日本人は、進学や就職によって生まれ育った故郷から都会へ移り住みます。当然、税金も住んでいる都会へ納めます。すると、都会の自治体と故郷の自治体とでは税収に格差が生まれてしまうのです。それならば自分が成長していく過程でお世話になった場所に、自分で納税できる制度があってもよいのではないか、という意見からふるさと納税制度が生まれました。
「納税」と名はついていますが、実際の手続きは自分の好きな都道府県や市区町村へ「寄付」になります。一般的に、自治体などに寄付をした場合、確定申告で「寄附金控除」の申請をすることで、寄附金額の一部が所得税や住民税から控除されます。
ふるさと納税も寄付金控除制度の一つですが、計算方法などが異なります。
まず、ふるさと納税は、納税を行う人の給与収入や家族構成によって納税の上限額が設定されています。上限額以内であれば全額が所得税、住民税から控除可能です。
例えば「年収700万円 夫婦+子ども2人(高校生と大学生)」という世帯であれば、上限額の目安は「75,000円」です。
ご自身の上限額を知りたい場合は、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」内にある「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」や「寄附金控除額の計算シミュレーション」を利用してみましょう。
「ふるさと納税ポータルサイト」
<ふるさと納税における控除の計算方法>
ふるさと納税における控除には、「①所得税の控除」「②個人住民税の控除(基本分)」「③個人住民税の控除(特例分)」の3種類があります。①と②で全額を控除しきれない場合は、③が適用されます。
① 所得税→所得金額から「ふるさと納税額(総所得金額の40%を限度)−2,000円」が所得控除されます。結果として、以下で算出される金額が還付金として返ってくることになります。
(ふるさと納税額−2,000円)×所得税率(0〜45%)
※所得税率は国税庁のホームページに掲載されています(令和19年の納税までは所得税率が0%である場合を除き、復興特別所得税を加算した率)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
② 個人住民税(基本分)→「ふるさと納税額(総所得金額の30%を限度)−2,000円」の10%が税額控除となり、ふるさと納税を行なった翌年の住民税が減額されます。
(ふるさと納税額−2,000円)×10%
③ 個人住民税(特例分)→「ふるさと納税額(住民税所得割額の20%を限度)−2,000円」に所得税率を乗じた金額が税額控除となり、ふるさと納税を行なった翌年の住民税が減額されます。
(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%(②基本分)−所得税率(※)
※③の計算時においては、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率を適用します
ふるさと納税を使って寄附をすることによって所得控除や税額控除が行われ、その年に納めた所得税の還付や翌年に納める住民税の減額を受けられます。
つまり、ふるさと納税は2,000円の自己負担はありますが、本来支払う税金を寄附という形で前もって納めているのです。冒頭に「税金を減らす制度ではない」とお伝えしたのはそのためです。
ちなみにふるさと納税は原則、確定申告が必要ですが、給与所得者で寄附先が5自治体以内など条件をクリアすれば「ワンストップ特例制度」を使って確定申告不要で手続きできます。その場合の控除は、住民税のみとなります。
2.ふるさと納税はなぜお得?
ふるさと納税で納められた寄付金は、地域活性化、復興支援、子育て支援、文化遺産や環境の保護などに活用されます。自治体によっては、寄附をする人が使い道を指定できるケースもあります。
では、減税されるわけではないのに、なぜふるさと納税がお得と言われるかいうと、多くの自治体では「返礼品」といって寄附に対するお礼の品を用意しているからです。
例えば、地域で栽培された野菜や果物などの特産品、工芸品、宿泊券など実にバラエティ豊かです。それらを2,000円の自己負担だけで受け取れる、というのがふるさと納税のお得な点であり大きな魅力です。
ただし、年収や家族構成などによってふるさと納税を行える上限額は異なりますし、返礼品の価値は「寄附金額の3割以下」と定められています。そして、寄附する際は手持ち資金の支払いが必要です。
所得税・住民税が発生しない人、控除上限額が7,000円未満となる年収の人、寄附に回せる資金がない人は、ふるさと納税のメリットを享受できない可能性があるので、注意しましょう。
3.最新のふるさと納税事情
各自治体の返礼品は、地域の特産品に限りません。
例えば、トイレットペーパーやお米などの生活必需品はとても人気があります。昨今の物価高騰も相まって、さらに注目が集まっているようです。また野菜や肉、魚介類といった食べ物は定番ですが、例えば「ふるさと納税だけで手に入る限定ラベルのお酒」などふるさと納税ならではの品物なども人気が高いです。
物品だけではなく、「無人島への宿泊券」「アミューズメントパークの入場券」「ヘリコプター貸切券」「茶摘み体験」などの体験系、「がん検査キット」「自分だけのオリジナル靴の仕立て券」などユニークなものもあります。お米でも、田んぼの一部スペースのオーナーとなって、自分で米作りができるといった面白い返礼品もあります。
そうしたさまざまな返礼品を見てまわるのも、ふるさと納税の楽しみのひとつといえるでしょう。
4.まとめ
ふるさと納税は誕生から15年以上経ちますが、独立行政法人経済産業研究所の調査によると2023年度、納税義務者に占める制度利用率は約16.7%(※)で、まだ利用したことがない人も多くいます。
税金を納めることは、言うまでもなく国民の義務です。しかし、それらが一体何に使われているのか疑問に思うことも少なくありません。それならば、自分が応援したい地域、思い入れのある地域の発展のため、あるいは自分や家族が欲しいもの、体験したいことなど、使い道が明確なふるさと納税を活用したいものです。
寄附先は生まれ育った土地に限らず、好きな場所を選択できます。そして、ほとんどの地域が、ふるさと納税の受け入れ額の実績や活用状況を公表しています。子育て支援や環境保全、動物愛護、災害復興など自分が興味・関心のある分野に寄附することで、大切な資金が有意義に使われていることを実感できるでしょう。ぜひ色々調べて「ここにぜひ納税したい」と思う地域を見つけてみてください。
ふるさと納税は1年を通して利用できますが、毎年1月1日から12月31日までにおこなった寄附が、当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となります。年末は駆け込みで利用する人が多くなりますので、手続きは早めにすることをおすすめします。
注釈:
(※)独立行政法人経済産業研究所のホームページより引用
https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/konishi-yoko/05.html#note3
参考:
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html)
国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm)