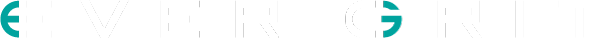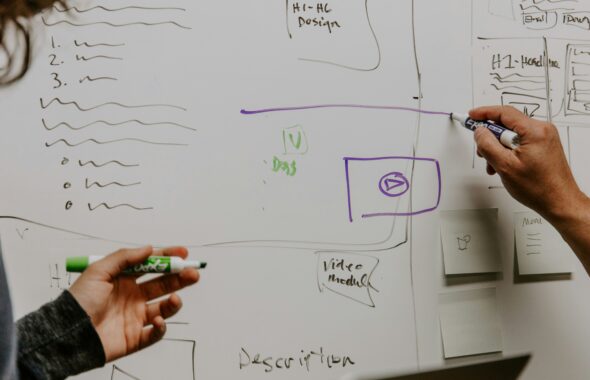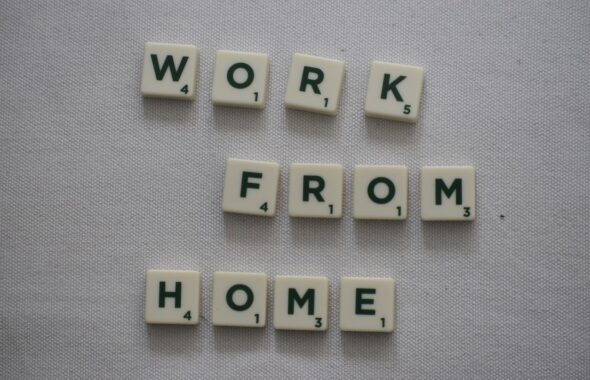【不動産勉強】賃貸仲介はどのような仕事をしているか?業務の仕組みを紹介します!
不動産の勉強をするには、賃貸仲介事業の仕組みを理解するのも役立ちます。賃貸管理事業の業務内容や収益の仕組みを知れば、不動産ビジネスの構造の理解に近づくからです。
今回は不動産業界の中でも賃貸仲介事業に焦点を当て、業務範囲や収益の仕組みから、裏側にある営業の優先順位まで解説します。
1. 賃貸仲介事業の業務範囲
賃貸仲介事業とは、借りたい人(入居希望者)と貸したい人(オーナー)の間に立ち、契約成立までをサポートする仕事です。具体的な業務範囲は以下のとおりです。
<ヒアリング・物件提案>
まずは、不動産ポータルサイトなどから問い合わせをした、または店舗へ来店した入居希望者に対し、家賃やエリア、間取り、築年数などの希望条件をヒアリングします。次にレインズと言われる不動産物件システムを使って条件に合う物件を探し、入居希望者に提案します。
<内見の調整・案内>
入居希望者の気に入る物件が見つかれば、現地の内見を行うのが一般的です。最近では、スマホやパソコンで部屋を確認するオンライン内見も増えています。
<申し込み・審査>
入居希望者が物件の申し込みをすると、管理会社による審査が行われます。職業な年収などの情報をもとに、「家賃の支払い能力があるか」「入居後にトラブルとなるリスクはないか」などをチェックされます。
<契約手続き>
審査が通過したら、いよいよ契約です。重要事項説明により契約内容を確認し、賃貸借契約を締結します。火災保険・保証会社の契約や初期費用の精算など、あらゆる手続きを行います。
<鍵の引渡>
最後に実施するのは鍵の引渡です。仲介会社としての仕事はここまでとなりますが、自社で管理している物件であれば、入居後も各種問い合わせや設備トラブルに対応します。
2. 賃貸仲介事業の主な収入源
賃貸仲介業者の主な収入源は、主に2つです。
<仲介手数料>
賃貸仲介事業の収入の柱となるのは、契約成立時に入居者とオーナーから受け取る仲介手数料です。
宅建業法では、入居者とオーナーのそれぞれから受け取れる手数料の上限は「賃料の0.5か月分以内」と定められています。依頼者の承諾があれば、どちらか一方から賃料の1か月分以内までの手数料を受けることも可能です。
入居者から1か月分を受け取るケースが散見されますが、オーナーからも手数料を得る場合もあります。
<AD(広告料)>
ADとは広告料のことで、オーナーが仲介会社に支払うことのあるインセンティブです。ADを支払うのは、「この物件を早く決めてほしい」と考えているからです。
ADは家賃の1か月分~2か月分が一般的で、仲介会社にとっては大きな収益源となっています。
3. 賃貸管理事業も行っている会社では、仲介する優先順位がある?
賃貸仲介事業と賃貸管理事業の両方を行っている会社も存在します。仲介と管理をどちらも担う会社では、物件の紹介優先順位に独自の事情が潜んでいます。仲介手数料だけでなく自社管理物件への誘導もポイントとなるからです。
自社管理物件の契約が決まれば、入居後もオーナーから毎月の管理料(家賃の3〜5%程度)が得られます。そのため長期的な目線で考えると、自社管理物件の契約を獲得した方がより多くの利益を得られるのです。
「不動産会社に部屋探しをお願いしたら別の物件をいくつも提案された」という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
問い合わせた物件が「既に申し込みが入っている」「条件が合わない」などと言われ、別の物件を勧められる場合、自社管理物件、またはAD(広告料)が高い物件の可能性があります。
また、営業担当としてはノルマの関係で、決まりやすい物件を優先しがちです。可能な限り内見した当日に申し込んでもらうことを目標に動いています。
入居希望者の視点で考えると、賃貸仲介事業や賃貸管理事業のこれらの事情を知った上で、本当に自分に合う物件かを見極める必要があります。内見時に即決を迫られた場合、一旦持ち帰って冷静に検討するのも大切です。
一方、オーナーとしてはリフォームの段階で検討を重ね、賃貸仲介会社が決めやすい物件に仕上げなければなりません。設備だけでなく、内見時の印象やADを含めた販促設計まで戦略的に考えることが求められます。
4.まとめ
賃貸仲介事業は、単に物件を紹介する仕事ではなく、営業利益や自社管理物件との関係、AD(広告料)の影響など、さまざまな要因が絡み合うビジネスです。
このような裏側の仕組みを理解すれば、不動産についての知識が深まります。自身が物件を借りたり貸したりする際も、より納得感のある取引ができるようになるはずです。
不動産について勉強するときは、各事業の仕組みを考えてみてください。