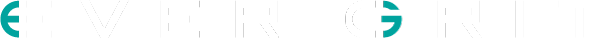節税対策ってどういうこと?
今回は収益不動産に関連した「節税対策」について話をしていこうと思います。
この記事からは下記のことがわかります!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①節税と脱税の違い
②結局節税は納税の先送り
③収益不動産の長期保有はその分納税リスクが増える
④まとめ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①節税と脱税の違い
前提条件として、この2つは大きく異なります。
節税と脱税の違いは、「合法性」にあります。
節税(タックス・プランニングまたはタックス・セービング)とは、法律の許す範囲内で税金の負担を減少させる方法を指します。企業や 個人が税法に従って利用できる控除やクレジット、税制優遇措置などを利用することで、支払う税金を減らすのが目的です。
一方、脱税(タックス・エヴェイジョン)は、不正手段を用いて税金を支払わない行為を指します。これには所得を隠したり、偽の情報を税務申告に提出するなど、違法な手段が含まれます。脱税は犯罪であり、発覚した場合には罰金や刑事罰を受けることがあります。
簡単に言うと、節税は法律の枠内で行われる合法的な活動ですが、脱税は法を犯す違法行為です。
実務上は、節税と脱税は紙一重のようではありますが、この「法律に抵触するかしないか」という観点で、大きく異なります。
しかし、過度な節税は、脱税とみなされるリスクがあります。
例えば、過度な経費申請。
経費といっても、事業に必要なものがあった場合や、売上をあげるために必要なものの場合、
経費として計上することが認められています。
不動産投資などでは、実際に自らの体を動かして収益をあげるモデルではないため、
営業活動として、売上以上の過度な会食経費を接待交際費として計上すると、
本当に売上に直結しているかということを問われることになります。
会社員の方々も取引先との会食の際に、会社へ経費申請をすることがあると思います。
その際、取引先の会社名や同席した方々のお名前、人数などを記載することになっていませんか?
もちろん会社員の方々の経費申請は、事業継続のために必要な経費と社内で認められているため、
突然、経費について問われることはありません。
ただ、個人事業主の場合は、会社=個人のため、適切な経費申請処理をしておかないと、
あとから調査が入った時に、経費が否認される可能性があります。
しっかりと税法上のルールを守りながら、合法的に許されている範囲内で、節税をおこなっていくことが大切です。
②結局節税は納税の先送り(償却してもその分、売却の際には利益とみなされる)
節税ときくと、今まで払っていた税金を抑えることができるので、得をしているように感じることがあります。
ただ、実際のところは、納税するタイミングを先送りにしているという状況とあまり変わりがありません。
例えば、不動産の売買を行なった場合には、短期譲渡税と長期譲渡税という税金が関わってきます。
確定申告で、不動産収入がある方々が、他の給与収入等と合算できることとは、全く別で、
不動産の売買の場合は、株式投資のように、「分離課税」が採用されています。
分離課税とは、所得税制の一部で、特定の所得に対して一般の所得とは別に税率を適用し、課税する方法を指します。
この制度は、所得の種類に応じて税率を変えることで、より適切な税負担を実現することを目的としています。
分離課税の対象となる所得には、以下のようなものがあります(国や制度によって異なる場合があります):
- 配当所得 – 株式などから得られる配当に対して特定の税率を適用。
- 譲渡所得 – 不動産や株式の売却から生じる利益(キャピタルゲイン)に対して適用されることが多い。
- 一時所得 – 一時的に大きな収入が入る場合(例えば、宝くじの当選金)に適用されることがある。
- 退職所得 – 退職金に対して適用される税率。
分離課税の特徴は、これらの所得が他の所得と合算されずに独立して課税される点にあります。
この方式により、所得の種類に応じて適切な税率が適用され、税の公平性が高まるとされています。
分離課税が採用されているということは、給与収入と関係なく、得られた利益に対して税金がかかるようになっています。
収益不動産の売買の場合は、減価償却をしたあとの簿価を取得価格として、計算をします。
そのため、減価償却で経費計上して節税し、所得税の還付を受けたとしても、
その減価償却が終わった後(法定耐用年数を超過した後)に、売却をしようとすると、取得価格0円の不動産を売却することになります。
売却した金額から取得価格を引いて税率をかけるため、ほとんどが利益となり、その分税金がかかってきます。
このように、減価償却で節税をしたとしても、別で税金を収める仕組みになっています。
「節税対策で不動産を」という広告をよく拝見いたしますが、その方それぞれで、給与収入が違えば、支出も異なります。
それぞれのステータスを正確に把握して初めて、節税対策ができるということを理解する必要があります。
③収益不動産の長期保有はその分納税リスクが増える!?
納税リスクが増える可能性があるのは、「法定耐用年数を超過し、減価償却費が計上できなくなる。」ことが理由にあげられます。
不動産投資で、節税対策の観点における魅力の一つに、減価償却費を計上できることがあげられます。
築年数が法定耐用年数を超えた場合の計算方法は「 耐用年数=法定耐用年数×0.2(端数切り捨て)」となります。
木造の場合は、法定耐用年数は22年のため、22×0.2=4.4(端数切り捨て)≒4.0年となります。
RC造の場合は、法定耐用年数は47年のため、47×0.2=9.4(端数切り捨て)≒9.0年となります。
中古物件を購入する際には気をつけなければいけないのは、この法定耐用年数の残存年数です。
こちらを超過すると基本的に建物代の簿価は0円ということになり、建物分の減価償却費が計上できなくなります。
そうするとどうなるか。
月々の家賃収入やテナント収入から管理費や固定資産税が引かれたあとの収入が、給与収入に合算されることになり、
結果、所得税が増税になります。
また、売却する際にも、納税となります。
特に中古のRC造は簿価は0でも、固定資産税評価額はまだまだ高い傾向にあるため、
建物代にも値段がつきます。
その建物分はまるまる利益となるので、分離課税で、長期譲渡税がかかります。
持っていても所得税があがる、売却しても譲渡税がかかる。
今まで節税した分と同額ではありませんが、ここで納税することになるわけです。
④まとめ 償却期間に応じた所有計画を立てましょう。
長期保有する計画で収益不動産を購入するためには、償却期間に応じた所有計画を策定し、
税理士と一緒に計画をたてて、効率的な節税を目指す必要があります。
当社では、5年ごとに、売却と所有のどちらも検討できる状態にしておくことをおすすめしています。
こちらの記事を書いている現在では、円安が加速している市況となっています。
円安が続くと、海外投資家などが、割安な日本の不動産を検討することになります。
中古市場の在庫が減ると、中古市場の価格が上昇します。
こういったように、経済市況にも影響を受けるのが不動産市況です。
その中、20年や30年でローンを組み、完済した際に、不動産価格は購入時よりどうなっているのでしょうか。
正直当社としては、どうなっているのか、わかりません。
ただ、5年くらいなら、大きく変動する可能性が低いので、手堅く資産を増やしていく方には、おすすめしております。
個人と法人で所有目的が違えば、所有期間も変わってきます。その年度の給与収入や年齢によっても、計画が変わりますし、
ご自身の年収推移によっても、今後の節税計画は大きく変わります。
そのため、本やインターネットからの情報を、そのままご自身にあてはめられないことがあります。
「収益不動産を所有して節税」といっても、本当にその人それぞれのアプローチがあることをぜひ覚えていただけたらと思います。