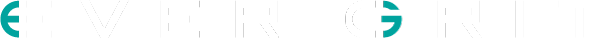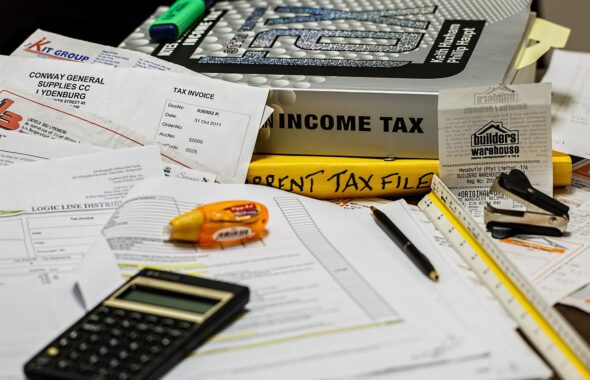短期譲渡税と長期譲渡税のあらましと注意点
今回は不動産取引における税金の中でも、意識しておかなければいけない「短期譲渡税」と「長期譲渡税」について、ご紹介していきます。
あらましの部分や、取引でどういった点で気をつけなければいけないのかということに焦点をあてて、お話していきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・短期譲渡税と長期譲渡税のあらまし
・不動産取引における譲渡税の計算時に気をつけるべきこと
・まとめ
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
短期譲渡税と長期譲渡税のあらまし
短期譲渡税と長期譲渡税は、財産の譲渡(売却)に関する税金で、保有期間に応じて税率が異なります。
以下にそれぞれの概要を説明します。
短期譲渡税
短期譲渡税は、財産を短期間(一般的には5年以下)保有した後に売却した場合に適用される税金です。具体的な特徴は次の通りです。
対象財産:不動産、株式、その他の資産。
保有期間:一般的に5年以下。
税率:短期譲渡税の税率は長期譲渡税よりも高く設定されることが多く見受けられます。
具体的な税率は国や地域によって異なるが、例えば日本の場合、
短期譲渡所得に対する所得税率は39.63%(住民税を含む)となっています。
課税方法:譲渡所得は、譲渡価格から取得費用や譲渡費用を差し引いた差額に対して課税されます。
長期譲渡税
長期譲渡税は、財産を長期間(一般的には5年以上)保有した後に売却した場合に適用される税金です。具体的な特徴は次の通りです。
対象財産:不動産、株式、その他の資産。
保有期間:一般的に5年以上。
税率:長期譲渡税の税率は短期譲渡税よりも低く設定されることが多く見受けられます。
例えば日本の場合、長期譲渡所得に対する所得税率は20.315%(住民税を含む)となっています。
課税方法:譲渡所得は、譲渡価格から取得費用や譲渡費用を差し引いた差額に対して課税されます。
日本における具体例
日本の場合、不動産の譲渡所得に対する短期譲渡税と長期譲渡税の税率は以下の通りです。
短期譲渡所得(保有期間が5年以下):所得税:30%、住民税:9% 合計:39%
長期譲渡所得(保有期間が5年超):所得税:15%、住民税:5% 合計:20%
短期譲渡税と長期譲渡税は、財産の保有期間に基づいて異なる税率が適用される税金です。
一般的に、短期譲渡の方が高い税率が適用され、長期譲渡の方が低い税率が適用されます。
具体的な税率や適用条件は国や地域によって異なるため、詳細は該当する税務当局のガイドラインを確認することが重要です。
不動産取引における譲渡税の計算時に気をつけるべきこと
この計算をする際に、重要な要素になってくるのは「減価償却費」です。
譲渡税の計算のために必要な譲渡所得の計算式は、下記の通りです。
譲渡所得 = 譲渡価格※売却価格 -(取得費用 – 減価償却費累計額)- 譲渡費用※売却にかかった費用
この計算式の中にもありますが、取得費用から減価償却費を差し引くことになります。
減価償却とは、不動産の取得費用をその耐用年数にわたって少しずつ経費として計上する会計処理のことです。
これを考慮することで、正確な譲渡所得が算出され、適正な税額が計算されます。
つまり、不動産投資は減価償却で節税をすることは可能ですが、売却した際に減価償却した分はそのまま利益として計算されることになっています。
別の記事でも書きましたが、「節税は納税の先送り」でご紹介している話とつながってきます。
よく、中古1棟RCで法定耐用年数の半分以上減価償却している案件を売却する際に、もちろん売却する金額にもよりますが、購入価格で売却するとしても、譲渡税の納税額は計り知れないほど大きくなっていることがあります。
そうなると、
売却したくても、売却できない。
売却できないで、所有していると修繕が多数発生して、費用がかかり、金融機関への毎月の返済に影響する。
このような状況になってしまうこともあります。
まとめ
収益物件の購入の際には、いつ頃いくらぐらいで売却するのかという出口戦略と合わせて、譲渡税の計算の必要性を伝えています。
いずれ売却するとしても5年は保有する。など、購入する時からご自身の不動産所有計画を見直して、不動産業者様と相談しながら
購入を検討するようにしてください。