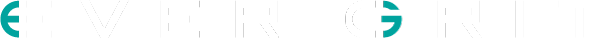意外と知られていない法人設立した後、必要な届出5項目
今回は「意外と知られていない、法人設立した後、必要な届出5項目」ということで、前回ご説明した法人設立のステップにおいて、最後の作業として必要な5つの届出についてご紹介していきます。
この届出をおこたると、後に色々なところから届出が完了していないことの連絡がきたり、気づいたら納税していなかったということになりかねないため、注意が必要です。一般的には、顧問税理士が届出をしてくれているはずですが、こちらから税理士に届出をしているかどうかの確認ができるように、あらかじめ知っておきましょう。
①法人設立開設届出書とは?
法人設立開設届出書は、新たに法人を設立した際に、所管の税務署にその設立を通知するために必要な書類です。
この届出書は以下のような目的と必要性があります。
1. 税務署への報告義務
法人が設立されたことを税務署に知らせることで、適切な税務処理が行われるようにするためのものです。これには法人税、消費税、事業税などの税目が含まれます。
2. 税務管理
法人設立後の税務処理をスムーズに進めるために必要です。法人の設立に伴い、税務署はその法人に関する税務管理を開始します。
3. 法人の登録
法人設立開設届出書を提出することで、法人が正式に税務署に登録されます。これにより、法人は税務署からの各種通知や指導を受けることができます。
4. 適切な税率の適用
法人の設立日や事業内容によって適用される税率や税制優遇措置が異なる場合があるため、それらを適切に適用するために必要です。
提出期限
一般的に、法人設立開設届出書は法人設立後1ヶ月以内に提出することが求められます。設立届出書には、法人の基本情報(名称、所在地、設立日、代表者など)や事業の内容、株主や役員の情報などが記載されます。
法人を設立する際には、必ずこの届出書を忘れずに提出し、適切な税務処理を行うための第一歩を踏み出しましょう。
②青色申告承認申請書とは?
法人が青色申告を行うためには、青色申告承認申請書を税務署に提出し、承認を得る必要があります。青色申告は白色申告に比べて多くの税務上のメリットがあるため、この申請書の提出は非常に重要です。以下に、その必要性と目的を説明します。
1. 青色申告のメリット
法人が青色申告を行うことで、以下のような税務上のメリットを享受することができます。
・青色申告特別控除:一定の条件を満たすと、様々な控除を受けることができ、税負担を軽減することができます。
・欠損金の繰越控除:事業で生じた赤字を翌年以降10年間にわたって繰り越し、利益と相殺することができます。
・引当金の計上:将来の支出に備えるための引当金を経費として計上することが認められます。
2. 正確な帳簿の記録
青色申告を行うためには、日々の取引を正確に記帳し、帳簿を整える必要があります。これにより、法人の財務状況を正確に把握し、適切な経営判断を行うことができます。個人と比べて法人の場合は、正確な帳簿をおこなうことは、必然的におこなっているため、青色申告の要件をみたすことができています。
3. 信用力の向上
青色申告を行うことは、税務署に対して適正な経理処理を行っていることを示す証拠となります。これにより、金融機関や取引先からの信用が高まり、融資を受けやすくなるなどのメリットがあります。
金融機関によるかもしれませんが、経験上では、ほぼ100%といっていいほど、決算申告書の内容について正確さが求められます。
正確じゃない可能性のある申告書は金融機関担当者としてもリスクでしかないため、その書類をもとに融資を申し込まれても辞退せざるを得ません。不動産投資においては、金融機関との関係性も大切です。信用の毀損がないようしっかりと帳簿をつくれることを示していきましょう。
提出期限
青色申告承認申請書は、新たに法人を設立した場合、その設立日から3ヶ月以内に提出する必要があります。また、既存の法人が青色申告に変更する場合は、その年の事業年度開始の日から3ヶ月以内に提出する必要があります。
青色申告のメリットを最大限に活用するためには、早めの申請と適正な帳簿管理が重要です。
③給与支払事務所等の開設届出書とは?
法人が代表者に役員報酬を、従業員に給与を支払う場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書の提出は、適切な税務処理を行うために非常に重要ですが、社会保険料の支払ともつながってくるところになるため、仮に役員報酬や給与の支払がなかったとしても、その「ないことの届出」もする必要があるため、理解しておきましょう。
1. 給与支払いの適正な管理
法人が従業員に給与を支払う際には、源泉徴収を行い、適切に税務署にたいして、源泉徴収した所得税を納付する必要があります。給与所得者(いわゆるサラリーマン)は給与明細において、会社が源泉徴収をおこない、天引きされているはずです。その辺りをイメージしていただくと理解が早いかもしれません。
この届出書を提出することで、法人が給与支払事務所を開設し、給与支払いに関する税務処理を行う準備が整ったことを税務署に通知します。
2. 源泉徴収義務の明確化
法人は、この届出により源泉徴収義務者として登録され、適切な税務指導や通知を受けることができます。源泉徴収というものがなぜ必要なのかということについては別記事で紹介したいところですが、簡単にいうと、所得税を納めない納税者が出てくる可能性があるため、あらかじめ給与から天引きすることによって、未納を防ぐためであることが推察できます。この源泉徴収義務を会社に負わせることによって会社は従業員から天引きする必要がでてくるのです。
3. 税務署からの指導・サポート
給与支払事務所等の開設届出書を提出することにより、税務署は法人に対して源泉徴収や納税に関する指導やサポートを提供します。これにより、法人が適切に税務処理を行うことができ、税務リスクを減少させることができます。
提出期限
新たに法人を設立し、給与支払事務所を開設する場合、設立日から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する必要があります。既存の法人が新たに給与支払事務所を開設する場合も、開設日から1ヶ月以内に提出することが求められます。
源泉所得税の納期の特例の承認申請書とは?その必要性と目的
法人が従業員に給与を支払う際には、源泉所得税を徴収し、定期的に税務署に納付する義務があります。「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」は、この源泉所得税の納付に関して特例措置を受けるために提出する書類です。以下に、その必要性と目的を説明します。
1. 納期の特例とは
通常、源泉所得税は毎月従業員の給与から天引きをして徴収し、翌月10日までに全社員分を納付する必要があります。しかし、納期の特例が承認されると、年2回(1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月20日まで)にまとめて納付することができます。
2. 事務負担の軽減
源泉所得税の納期の特例が承認されると、毎月の納付作業が不要になり、年2回の納付で済むため、事務処理の負担が大幅に軽減されます。このこの特例については、従業員数10名未満の場合に適用されます。設立まもない会社に事務的な負担がかからないようにという意図もあるため、
会社全体の工数をさげることができます。
3. 資金繰りの改善
納期の特例を利用することで、毎月の納付を避けることができ、一時的に資金を手元に置いておくことができます。これにより、法人の資金繰りが改善され、より柔軟な資金運用が可能になります。
4. 法的義務の遵守
「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を提出し、承認を得ることで、正式に特例措置を利用することができます。これにより、法的に認められた手続きの下で、源泉所得税の納付を行うことができ、適正な税務処理が保証されます。
提出期限
新たに法人を設立した場合や、既存の法人がこの特例を希望する場合は、申請書を所管の税務署に提出し、承認を受ける必要があります。通常、特例の適用開始を希望する月の前月末までに提出することが求められます。
消費税課税事業者選択届出とは?
「消費税課税事業者選択届出」は、法人が自ら消費税の課税事業者を選択するために提出する書類です。通常、一定の条件を満たす場合を除いて新設法人は消費税の免税事業者となりますが、この届出を提出することで課税事業者として登録されます。以下に、その必要性と目的を説明します。
1. 消費税の仕入税額控除を受けるため
消費税課税事業者となることで、仕入れや経費にかかる消費税(仕入税額)を控除することができます。これにより、納付する消費税額を減少させることができ、実質的な税負担が軽減される場合があります。
2. 信用力の向上
課税事業者として登録されることは、取引先に対して信頼性を示す一つの要素となります。特に大規模な取引先や法人間の取引では、課税事業者であることが信用力の向上につながる場合があります。
3. 事業規模の成長への対応
事業が成長し、年間の売上高1,000万円を超えると、その超えた事業年度の2年後から免税事業者から自動的に課税事業者となります。予め課税事業者を選択しておくことで、将来的な消費税の対応に備えることもできます。
4. 不動産投資における届出の意味
本届出自体には色々なメリットがありますが、不動産投資においては、少し意味合いが変わってきます。2010年代に不動産を法人名義で購入して、建物代の仕入課税控除を受けることが非常に流行った時期がありました。いわゆる「消費税還付スキーム」という方法になります。この建物消費税分の還付を受けるために、不動産の購入において、法人設立が流行ったといっても間違いではありません。
しかしこちらについても法改正により、現在では「居住用賃貸建物における仕入課税控除については認められない」となっているため、現在はこちらの届出を提出したとしても、消費税還付を受けることは現実的に難しいとされています。
提出期限
「消費税課税事業者選択届出」は、課税事業者としての適用を希望する課税期間の開始前日までに所管の税務署に提出する必要があります。新設法人の場合は、設立日から原則として2ヶ月以内に提出することが求められます。
ただ、この届出については、不動産投資で得られる収入が課税売上ではなく非課税売上であることから、そもそも課税事業者になる必要がありません。届出をおこなうかどうかについては、顧問税理士に相談の上、決定するようにしてください。
不動産賃貸業しか行っていない法人で、その売上が非課税売上のみの場合、届出の必要はないと、当社は考えています。
まとめ
法人設立後の必要な届出のご紹介をしました。5つありますが、その事業の目的によっては一部届出不要なものもありますが、基本的には消費税課税事業者選択届以外の4つについては全て届出が必要となりますので、顧問税理士に申請したかどうか念の為確認できるように、覚えておきましょう。