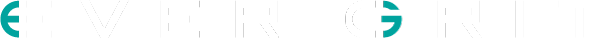確定申告の勉強をしましょう!①
今回は確定申告の変遷と、確定申告とはなんのためにするのか、確定申告をする必要がある人はどんな人かということなどがわかります。少し内容を分けてわかりやすくするため、2回にわけて紹介していきます。
もしかしたらサラリーマンの方々は確定申告している人は少ないと思いますが、今後必要になる可能性がありますので、一緒に勉強していきましょう。
確定申告とはなんのためにするの?
確定申告は、日本の税務システムにおいて、個人や法人が、1年間の所得や経費を申告し、収めるべき税額を確定するためにおこなうものです。国の大きな税収のひとつでもある、所得税はこういった申告納税制度により納められています。
日本には国民の三大義務というものがあり、そのうちの一つに「納税の義務」というものがあります。これは日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」 と定められています。つまり、日本で収入が発生している以上、納税は「義務」となっています。
皆さんがイメージしている税金は、所得税や住民税や消費税などが、よく聞く、身近な税金というイメージがあるかもしれません。
今回の記事では、「所得税」の確定申告を中心にお話をしていきます。なぜかというと、住民税はこの所得税の確定申告で申告した所得を参考にして税額が確定していくため、順序としては、所得税→住民税という順番で税額が決まってくるためです。また、住民税は所得金額にかかわらず定額を負担する「均等割」と、所得金額に応じて負担する「所得割」という2つの構造になっているため、住民税の金額は「均等割の金額 + 所得割の金額」で算出されます。さらに所得税は国税で、 住民税は市税、すなわち各市区町村に納めるなど、納める先も異なります。消費税においては、普段の消費活動で商品の価格に上乗せして、商品代金と一緒に、納付しています。正確にいうと、その支払先に「預けている」そういった性質のものになります。その預けた消費税は、事業者側が預かり、国税として、国に納付しています。また、消費税についてはその内容が複雑なため、消費税の申告書という、所得税とは別で申告書の作成をしてまとめて計算することが必要です。
このように、税金といっても、納める機関や、計算の仕方、考え方も異なるため、それぞれ別のものと考えてください。
確定申告をすると何がおこるの?
確定申告をすることで、下記のようなことがわかります
1.所得税の納税額
個人や法人が年間の所得金額を、確定申告書を作成していく中で、正確に計算して、その金額に基づいて、税額を計算することができます。計算された所得税は、期日までに納付が必要です。
2.経費の申告・税金の還付
サラリーマンの方々は給与明細で「所得税」として天引きされているものがあると思います。この金額はあらかじめ月額の給与に合わせて、源泉徴収税額が定められており、雇用主があらかじめ給与から天引き(源泉徴収)することが義務付けられています。あらかじめ給与の予測を立ててが天引きされているため、あくまでも「暫定数字」ということになります。この「暫定数字」で算出された金額が、他の所得や経費で差引されて最終的に納める税金が決まるのが確定申告のタイミングということになります。
そのタイミングで、もしかしたら給与所得以外の所得で損失を出していた場合、給与所得と合算すると、月額の給与から天引きされている所得税より、実際に納める金額が低くなる可能性があります。そうすると納めすぎたということで、還付(納めた税金が戻ってくること)を受けることができます。よく聞く「節税」というのは、こういった仕組みを利用しています。納めすぎた税金の還付を受けるために、節税商品を購入する方もいます。
3.控除の適用
医療費控除や扶養控除、生命保険料控除や地震保険料控除などがあります。そういったすでに支払ったものも、所得からあらかじめ控除することができます。そうすることで、税率をかける直線の金額を、さらに低くすることができるので、節税効果が期待できます。
まとめ
確定申告は、納税する金額を確定するとともに、ご自身の経費や控除額も確定させて、所得税の還付を受けることができる手続きです。内容をしっかりと理解することで、不要な部分を取り除いた、適切な納税をおこなうことができます。
次回は、確定申告をするの必要な方はどんな方なのかということを中心にご紹介していきます。