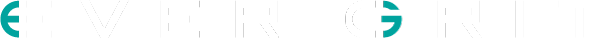【不動産 勉強】不動産投資で融資を受けるとき、金融機関は何を評価して融資をしているか?
不動産の購入は金融機関からの借り入れを前提とするケースが大半です。
不動産投資で利用できるローンなどの金融商品は多数存在しますが、「申し込んでも、審査が通らなかったらどうしよう」「借りられる額が減らされてしまったら……」と不安に思う方も少なくないでしょう。
では、不動産投資用のローンにおいて金融機関はどのような基準で融資の可否や貸し出しする金額を判断しているのでしょうか?
本記事では、審査で見られる主な5つのポイントを解説していきます。
1.物件そのものの担保としての価値
まずチェックされるのが「物件が融資の担保としてどれだけの価値を持つか」です。金融機関としては、万が一返済が滞った場合、その物件を売却し、貸したお金を回収することになります。ですから、物件の価値をしっかりと見極めるわけです。その際、一般的に用いられるのが「積算評価」という方法です。
■積算評価とは?
物件の「建物部分」と「土地部分」の価値を個別に算出し、合算した金額のことを指します。
積算評価=①土地の評価額+②建物の評価額
①土地の評価額
国や自治体が定める路線価や固定資産税評価額をもとに、「1㎡あたり○万円×面積(㎡)」で計算します。
②建物の評価額
同じ建物を新しく建てるとしたらいくらかかるか(再調達価額)を基準に、築年数に応じて価値が減少していく「減価償却」の考え方で評価されます。
国税庁が定める法定耐用年数(鉄筋コンクリート造なら耐用年数47年、木造なら22年など)から築年数を引いた残存年数を求め、
「建物評価額=再調達価格×(残存年数÷耐用年数)」で計算します。
例えば、以下のような不動産の場合、積算評価額は「1,000万+1,150万円
=約2,150万円」になります。
①土地の評価額
・評価単価:10万円/㎡
・土地の広さ:100㎡
10万円×100㎡=1,000万
②建物の評価額
・再調達価格:2,000万円
・構造:鉄筋コンクリート造
・法定耐用年数:47年
・築20年→残存年数は27年
2,000万円×(27年÷47年)=約1,150万円
積算評価は、特に地方銀行や信用金庫などが重視する傾向があり、評価額が融資額を上回れば、希望額での融資が通りやすくなります。
ここで注意が必要なのは、市場価格と積算評価のギャップです。
例えば、市場において3,000万円で売られている物件であっても、積算評価が2,000万円だった場合、融資は2,000万円までしか受けられないことがあります。そうすると残り1,000万円は自己資金の用意が必要になります。
そのため、不動産投資家の多くは「積算評価が出やすい物件」を探したり、「土地値で買える物件」を選んだりする工夫をしています。
2.物件の収益力がどれだけあるか
不動産投資は、基本的に「賃貸による収益を見込んだビジネス」です。そのため金融機関は、単純に土地、建物の価値だけでなく、「この物件が将来どれだけ安定した収益を生み出せるか」にも注目しています。
その価値を数値化するのが「収益還元法」で、とくに都市銀行や一部の投資用ローンでは、積算評価よりも「収益還元評価」が重視される傾向にあります。
■収益還元法とは?
「将来見込める家賃収入」から「経費(修繕費・固定資産税など)」を引いた純収益をもとに、物件の価値を算出する方法です。
物件の価値=年間の純利益÷想定利回り
たとえば、次のような物件の収益還元評価額は「80万円÷0.08=1,000万円」になります。
・月々の家賃収入:8万円
・年間家賃収入:96万円
・年間運営費(管理費・修繕費等):16万円
・純収益:80万円
・想定利回り8%
「安定した賃料収入を見込めるか」に加え、空室リスクや地域の需給バランスも合わせて審査されるため、購入予定物件周辺の賃料相場、空室率、過去の入居率のチェックも欠かせません。
「毎月の家賃で安定してローンを返していける物件」は金融機関の評価も高くなりやすく、融資が通りやすい傾向にあります。
3.購入者自身のステータス(属性)
物件の評価だけでなく、「買う人がどんな人か」も融資判断の大きな材料になります。
金融機関が確認するのは主に次の要素です。
・年収や勤続年数
・職業や勤務先の安定性(上場企業、医師、公務員などはプラス評価)
・預貯金や保有している不動産などの資産状況(自己資金が多いと有利)
・個人信用情報(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)
このように金融機関は、融資する相手の社会的信用や経済的状況をもとに「返済能力があるか」を見ています。
信用情報では、クレジットカードやローンの契約状況もわかります。滞納履歴があると、審査にマイナスとなることがあるので注意が必要です。
4.不動産投資の実績と経験
初めて不動産投資に挑戦する人と、すでに複数棟を保有して運用実績のある投資家とでは、金融機関の見方も変わります。
実績がある投資家の場合、次のような要素が判断材料になります。
・過去の運営状況(入居率、収益性)
・返済状況
・物件管理の体制(自主管理か、業者に委託しているか) など
審査では決算書の他に修繕や管理の履歴なども求められるケースもあるので、運用に関わる記録をしっかり残しておくことが大切です。
過去の運用実績から「不動産事業を継続できる能力がある」と判断されれば、2棟目、3棟目の融資もスムーズになります。
一方、投資が初めてという人であっても、「実績なし=融資が受けられない」とは限りません。個人の属性や物件の評価が審査基準を満たしていれば、融資を受けられるケースがあります。
5.保証会社の有無も重要な判断要素
最近では、不動産投資ローンで、「保証会社」を利用するケースが増えています。
保証会社は、万が一返済が滞った場合、借り手に変わって一時的に返済の立て替え(代位弁済)を行う「保証人」のような役割を果たします。
かつては金融機関から借り入れをする場合、親族などに保証人になってもらう必要がありました。しかし、保証会社を利用することで連帯保証人なしで借り入れができるようになったのです。
保証会社を利用するには保証料がかかりますが、借り手にとっても手間や精神的負担がなくなるメリットがあります。
また、保証会社が介在することで金融機関は貸し倒れのリスクを軽減できるため、融資の審査のハードルがぐっと下がります。
とくにメガバンクや一部のノンバンク系では、保証会社の利用が必須となっている場合もあります。保証会社の基準は金融機関以上に厳しいこともあるため、不動産会社と連携して事前準備を進めておくとよいでしょう。
まとめ
お伝えしてきたように、不動産投資で融資を受ける場合、金融機関には「物件の価値」だけでなく、「購入者自身の信用」や「投資実績」など、多角的に判断されます。金融機関の視点を押さえておくことは、物件選びや資金計画を戦略的に進めるうえでも重要なポイントです。
金融機関によって審査の基準や傾向だけでなく、金利や期間などの条件も異なります。事前にそれぞれの特徴を調べ、自分に合った金融機関を見極めることで、より有利な条件での融資を目指すことができるでしょう。
また、物件や個人の状況に応じて必要な資料を事前に準備をしておくことで、金融機関との信頼関係を築き、スムーズに融資を受けることができます。
まずはあなたが「どんな物件を、どんな目的で、どう管理していくのか」、投資プランを整理してみることから始めてみましょう。