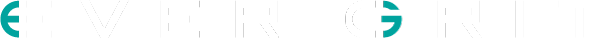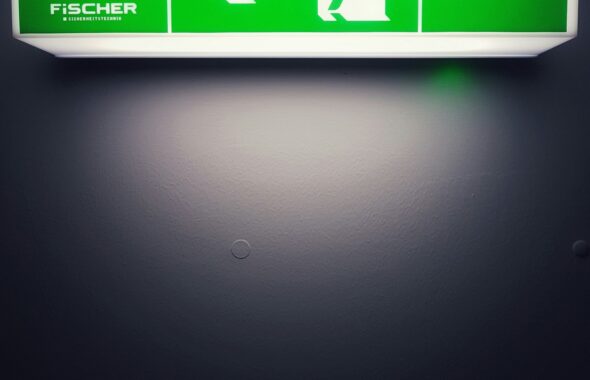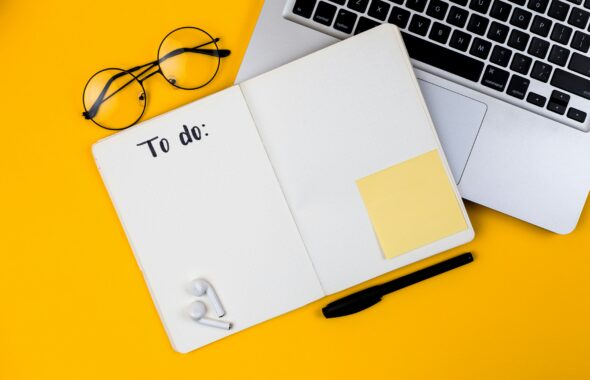【不動産 勉強】木造戸建の大規模リフォームで「確認申請」が必要に!?〜戸建投資における法改正のポイントをわかりやすく解説〜
2025年4月から、木造戸建のリフォームに関するルールが大きく変わりました。
これまでは「確認申請は不要」だったリフォーム工事も、内容によっては建築確認申請が必要とされるケースが出てきます。
———————————————
国土交通省:木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて
https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf
———————————————
空き家などの築古戸建てを取得し、再生・収益化していく投資において、このルール改正は決して無関係ではありません。
今回は、改正のポイントを解説するとともに、実務上の注意点や、どんな工事が申請の対象となるのかをお伝えします。
■「確認申請」とは何か?
まず、「確認申請」とは、建築物の新築・増築・改築などを行う際に、その計画が建築基準法に適合しているか、行政や指定確認検査機関の事前審査を受けるための手続きです。
これまで多くの木造戸建ては、簡易なリフォーム工事であれば確認申請は不要でした。これは、木造戸建てが建築基準法において、特に小規模な建築物に分類される「4号建築物」に該当していたからです。
しかし、法改正によって「4号建築物」が廃止され、階数2以上または延べ面積200㎡超の建物は「新2号建築物」として、確認申請の対象になります。
■確認申請が必要になるリフォームの内容とは?
確認申請の要否でポイントとなるのは、「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」です。
これは、建物の主要構造部(壁・柱・梁・床・屋根・階段)のうち、いずれか1種類以上について「過半の改修」を行う工事を指します。
例えば、以下のような工事が該当します。
・間取り変更を伴う耐力壁の撤去・新設
・屋根を骨組みからすべて葺き替える工事
・柱の半分以上を交換するような構造的改修
・2階への階段をかけ替えるような工事
このように建物の安全性や強度に関わる工事は、範囲を明確にし「過半に該当するかどうか」を慎重に判断する必要があります。
改修の手法やその範囲についての線引きは専門性が高く、複雑です。改修工事の内容を独断で判断したり、施工業者に任せきりにしたりせず、都道府県の建築士会、建築士事務所協会などに相談しておくと確実でしょう。
■申請が不要なケース
とはいえ、すべてのリフォームに確認申請が必要になるわけではありません。
以下のような内容であれば、これまで通り確認申請は不要です。
・キッチン、トイレ、浴室など水回りの設備交換のみ
・手すりやスロープの設置(バリアフリー化)
・床や壁のクロスの貼り替え、フローリングの上貼り
・小規模な間仕切壁の新設や撤去(構造に影響しない場合)
このように、柱や梁などの主要な構造部分に手を加えない改修工事であれば、確認申請は不要となるケースが多いとされています。特に、賃貸用として内装を整える程度のリフォームであれば、影響は少ないと言えるでしょう。
■改正の背景にある「安全性への懸念」
「確認申請が必要なったら、どうすればいい?」と疑問を持った方もいらっしゃるでしょう。その場合、建築士による図面作成や申請業務が必須です。これには、10〜50万円程度の費用がかかります。金額によっては、想定していた利回りが大きく下がる可能性もあります。
工期が長くなることも予想されますので、リフォーム投資を進める際には事前に建物の状態を把握し、確認申請を踏まえた修繕計画を練ることが重要です。
今回の改正の背景には、無資格の業者による最低限の工事や、DIYリフォームで高収益を得ようとする一部の投資家の存在があります。
活益化は戸建投資において欠かせない要素です。しかし、安全性を無視したリフォームや建物の運用は、事故やトラブルにつながるケースも少なくありません。利用者保護の観点からも規制が必要とされているのです。
一定の品質や安全性の基準を満たさない再生物件の流通を抑止するという意図も、今回の改正からは透けて見えます。今後は、「建物の構造に関わる工事は、建築士による設計・監理が必須である」という考え方が徹底される流れとなっていくでしょう。
■戸建投資家が今後気をつけるべきこと
これからの戸建て投資では、「確認申請」の要否を踏まえた投資戦略を練ることが重要です。
以下のポイントを押さえて、物件選定やリフォーム計画を進めましょう。
1.物件が「新2号建築物」に該当するかを確認する
→建物の規模が2階建以上または延べ面積200㎡超であれば要注意
2.「大規模修繕」に該当する工事を行うか否かを検討する
→主要な構造部(壁・柱・梁・屋根・床・階段)の過半を改修するか?
3.確認申請が必要な場合のコストとスケジュールを見込む
→利回り、工期、出口戦略を踏まえて投資計画を見直す
4.改修工事の内容は独断や施工業者任せにしない
→判断に迷う場合は、建築士・行政に事前相談をする
シロアリ被害や雨漏りなどがある物件では、確認申請が必要な大規模な改修が想定されます。物件を取得する段階から、建物の状態をしっかりと調査しておくことが重要です。
また、調査や相談にあたって収集した資料、写真、文書などは必ず保管しておきましょう。
■まとめ
今回の法改正では、住宅の安全性や品質の向上が求められていることがうかがえます。
戸建て投資を行う上では、法改正に対して「リフォームの自由度が下がる」「手間が増えた」とネガティブに感じた方もいるかもしれません。しかし裏を返せば、「安全性の高い物件」を流通させて、入居者の信頼を獲得するチャンスと捉えることもできます。
法改正の背景を正しく理解し、質の高い物件を提供することは、長期入居や家賃アップといった成果にもつながります。
今後は、「確認申請」の要否を踏まえた物件選定やリフォーム計画が、戸建て投資の成功の鍵と言えるでしょう。