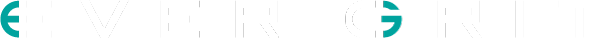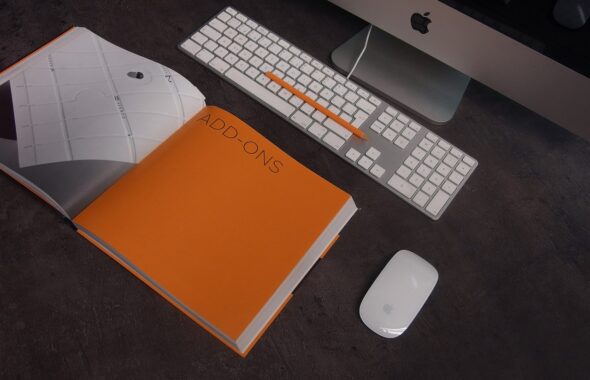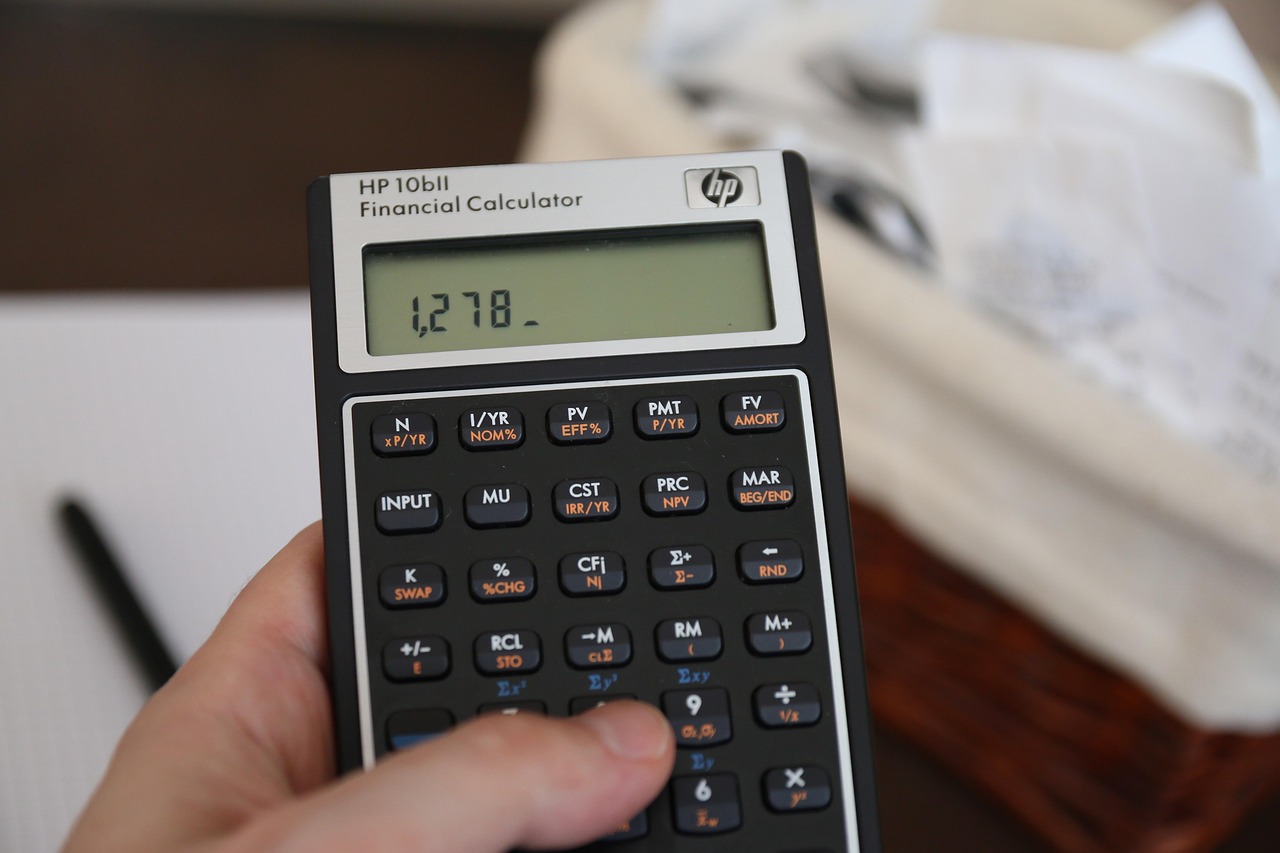
ふるさと納税は本当に節税になる?税金控除の仕組みを初心者にもわかりやすく解説
「ふるさと納税」と言えば、「節税になる」とイメージしている方は多いでしょう。
そのような方にはお伝えづらいのですが、実は、ふるさと納税は「節税」にはならないのです。
では、なぜ世間ではふるさと納税がお得と言われるのでしょうか。
本記事では、その疑問に対する答えと、税金控除の仕組みをわかりやすく解説します。
税金の知識に自信がないという初心者の方でも、理解しやすいようにお伝えしますので、安心して読み進めていただければと思います。
ふるさと納税が「節税」にならないのにお得なワケ
まず、最も重要な結論から先にお伝えしましょう。
ふるさと納税を簡単に説明すると、本来みなさんがお住まいの自治体に納める予定の税金(所得税や住民税)の一部を、みなさんが応援したい自治体へ「寄附」として前もって納められる仕組みです。
つまり、納める税金の総額が減るわけではないのです。そのため「節税」にはなりません。納めたい場所を選んで行う「税金の先払い」と言った方が、イメージしやすいと思います。
「それなら全然お得じゃない」と思われたかもしれませんね。
ふるさと納税がお得だと言われるのは、税金の先払いをすることで、寄附した自治体より返礼品をもらえる場合があるからです。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、返礼品は地域の名産品をはじめ、日用品や高級グルメ、宿泊券など多岐にわたります。
そうした魅力的な返礼品を、好きな地域を応援しつつ実質2,000円で手に入れられるのが、ふるさと納税の最大の「お得」な部分なのです。
所得税と住民税、それぞれの控除の仕組み
「えっ、2,000円!? どういうこと? 税金は?」とハテナマークがたくさん浮かんでいる方も安心してください。これからその仕組みについて解説していきますね。
ふるさと納税では、寄附をした金額のうち2,000円を超える部分について、「所得税」と「住民税」という2つの税金から控除されます。つまり、2,000円は自己負担となるのです。
例えば、あなたが好きな自治体に50,000円を寄附したとします。このうち自己負担額の2,000円を除いた48,000円が、翌年支払うべき所得税や住民税から差し引かれる(控除)のです。
そして、寄付のお礼として豪華なグルメや商品が手元に届きます。実質2,000円の負担で2,000円以上の返礼品を受け取れるケースもあり、その差額分はまるまるお得になる、というわけです。
では、所得税と住民税、それぞれの控除の仕組みにも触れていきましょう。
① 所得税からの控除 は「還付」として戻ってくる
会社員の方であれば、毎月の給与から所得税が天引き(源泉徴収)されていると思います。
「ふるさと納税したら、二重で納税されてしまうのでは?」と思うかもしれませんが、これは一時的なこと。
ふるさと納税を利用した場合、確定申告することで、払い過ぎた所得税が「還付」という形で、指定した口座へ後日戻ってきます。
② 住民税からの控除は「減額」される
住民税は、ふるさと納税を行った翌年に納める税金が安くなる、という形で控除されます。
確認方法は、毎年6月頃に会社や自治体から届く「住民税(市県民税)決定通知書」を見てください。
通知書の適用欄(ワンストップ特例を利用した場合)あるいは、税額控除額欄にふるさと納税の控除分が記載されます。
そして、翌年6月以降、毎月給与から天引きされる住民税の額が少なくなるのです。
このようにふるさと納税では、所得税と住民税が還付あるいは減額によって控除されます。
寄附をするときは、いったん全額自分で支払うことになりますが、最終的に自己負担額が2,000円となる仕組みになっているのです。
あなたの控除上限額を計算するには?
「自己負担2,000円なら、できるだけ高額の返礼品を選んだ方がお得」と思ってしまいますが、ちょっと待ってください。
ふるさと納税で最も注意しなければならないのが、「控除上限額」です。
これは、年間で寄附できる上限金額のことで、超えてしまった分は税金控除を受けられません。
控除上限額は、年収(所得)や家族構成(扶養家族の有無)、iDeCoや住宅ローン控除の有無などによって決まります。
正確な金額は複雑な計算が必要ですが、各ふるさと納税ポータルサイトには、控除上限額の早見表(目安)や、簡易の「控除上限額シミュレーター」が用意されています。
シミュレーターは給与収入や年齢、家族構成などがわかれば、誰でもすぐ調べられます。源泉徴収票などを手元に用意して、ぜひ試算してみてください。
手続き方法は2種類!確定申告とワンストップ特例制度
実際、ふるさと納税を利用したいときの方法にも触れていきましょう。
税金控除を受けるには、以下の2つの方法があり、ご自身の状況に応じて選択する形となります。
① ワンストップ特例制度
主に会社員や公務員の方が受けられるもので、以下の2つの条件をクリアできれば利用できます。
・年間の寄附先が5自治体以内
・もともと確定申告をする必要がない給与所得者であること
寄附を行うたびに自治体から送られてくる申請書に必要事項を記入し、必要書類などとともに返送します。自治体やポータルサイトにより、オンラインで完了できる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
ワンストップ特例を利用する場合、税金控除は住民税のみになります。
② 確定申告
自営業の方、医療費控除や住宅ローン控除(1年目)などで確定申告が必要な方、あるいは6自治体以上に寄附した方、2,000万以上の給与収入のある方などは、確定申告を行います。
確定申告は、ふるさと納税を行なった翌年の確定申告期間(原則2月16日〜3月15日)に申告を行います。
1年間の寄付を証明する書類が必要となるため、自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」はすべて保管しておきましょう。ポータルサイトによって、寄附情報をまとめたデータを取得できる場合もあります。
まとめ:仕組みを理解して、お得な制度を最大限活用しよう
ふるさと納税は、「節税」にはなりませんが、支払うべき税金の納め先を自分で選び、そのお礼として返礼品を受け取れるという、メリットの大きい制度であることは間違いないと感じています。
制度の恩恵をしっかり受けるためには、自分の「控除上限額」を正しく把握し、自分に合った手続き方法を正しく行うことが大切です。
ふるさと納税にチャレンジする際は、ぜひ、本記事の解説も参考にしていただけたらと思います。
節税や資産運用については、当社でもご相談を承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
参考:総務省ホームページhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/