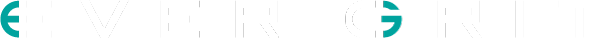不動産仲介で利益が出る仕組みとは?安心して取引するための基礎知識
マイホームの購入や実家の売却など、多くの人が人生で一度は経験する不動産の取引。
その際にお世話になるのが、「不動産仲介会社」です。物件探しから複雑な契約手続きまでサポートしてくれて、私たちにとっては頼りになる存在です。
しかし、「ただ間に入っているだけなのに、不動産仲介会社の利益はどこから生まれているの?」「もしかして騙されて多く請求されていたらどうしよう……」などと疑問や不安に思ったことはある方もいるはず。
結論から言うと、不動産仲介会社の利益の源泉は「仲介手数料」です。
よく聞く言葉でご存じの方も多いと思いますが、実はこの手数料には、法律で定められた上限額など、明確なルールが存在します。
この記事では、不動産仲介会社の利益となる仲介手数料の仕組みについてわかりやすく解説します。
正しく理解することで、不動産取引をより安心感と納得感を持って進められると思います。ぜひ読んでみてください。
不動産仲介会社の利益「仲介手数料」とは?
仲介手数料とは、不動産の売買や賃貸の契約が成立した際に、その成功報酬として不動産仲介会社に支払われる手数料のことです。
では、不動産仲介会社が具体的にどのような業務を行っているのかというと、その内容は多岐にわたります。
不動産売買を例に、売主側への業務、買主側への業務に分けて紹介します。
【売主側の主な業務】
・物件価格の査定
・売却の戦略を検討
・物件情報の広告作成や掲載など
・購入希望者募集と問い合わせ対応
・物件の内覧の手配や立ち会い
・購入希望者との価格や条件の交渉
・売買契約書作成や重要事項の説明
・引き渡しまでのスケジュール管理
【買主側の主な業務】
・希望条件のヒアリングや資金計画の相談
・条件に合う物件の紹介
・物件の内覧の手配と同行
・売主との価格や条件の交渉
・住宅ローンの手続きサポート
・売買契約書の確認と重要事項の説明
・引き渡しまでのサポート
こうした専門的な知識や労力を要する業務を、売主や買主の代理で行うことの対価が仲介手数料なのです。
ただし重要なポイントは、この仲介手数料が「成功報酬」であること。つまり、どれだけ広告活動や内覧の案内をしても、最終的に不動産の売買契約が成立しなければ、不動産仲介会社には1円も入ってきません。
そのためこの制度は、不動産仲介会社の営業担当者が契約成立に向けて直向きに取り組む大きな動機にもなっています。
仲介手数料の上限額と計算方法
「仲介手数料は高額」「業者によって差があるのでは?」とイメージされている方もいらっしゃると思いますが、実は仲介手数料は、不動産仲介会社が自由に設定できるわけではありません。
不当に高額な請求から消費者を守るために、宅地建物取引業法という法律によって、受け取れる上限額が厳密に定められているのです。
上限額は、「取引する物件価格に応じて、一定の料率を乗じて得た金額を合計した額」以内と定められており、以下の3段階に分かれています。
| 売買価格 | 上限手数料率(税抜) |
| 200万円以下の部分 | 5% |
| 200万円を超え、400万円以下の部分 | 4% |
| 400万円を超える部分 | 3% |
例えば、3,000万円で売買された物件の場合、以下のような計算になります。
① 200万円以下の部分を計算
200万円 ✖️5%= 10万円
② 200万円を超え400万円以下の部分を計算
(400万円 – 200万円) ✖️4%= 8万円
③ 400万円を超える部分を計算
(3,000万円 – 400万円) ✖️3%= 78万円
④ 1〜3の合計を計算
10万円 + 8万円 + 78万円 = 96万円
※税抜のため、これに消費税が加わります。
ただし、法律で定められているのはあくまでも「上限額」です。そのため、不動産仲介会社との合意があれば、上限額より低い手数料での取引も可能ですが、実務では多くの仲介会社が上限額を手数料として設定しているのが現状です。
仲介手数料の特例「低廉な空家等」の仲介では手数料が異なる
しかしながら、仲介手数料のルールは2024年7月から一部特例制度が設けられました。それは、物件価格が800万円以下の「低廉な空き家等」の売買における仲介手数料の上限額が「一律33万円(税込)」となったことです。
昨今は少子高齢化や人口減少などさまざまな要因から、全国で空き家の増加が社会問題化しています。空き家物件は、一般的な物件より安価な場合が多く、その場合、不動産業者が受け取れる仲介手数料が少なくなってしまいます。
しかし、それでは調査費用や人件費といったコストを十分にまかなえないという背景から、結果として空き家物件の取引を積極的に行う業者が減っている実態があるのです。
そこで、増加する空き家の取引を活発化する政策の一環として、このような取り組みが行われています。
なお、空き家物件の取引を行う際、業者は上記の特例について依頼者にきちんと説明を行って合意を取ることになっています。
利益が2倍に!?「片手取引」と「両手取引」
不動産仲介会社の利益を大きく左右する要因に、「片手取引」と「両手取引」という2種類の取引形態が挙げられます。それぞれどのようなものなのか見ていきましょう。
片手取引
売主側と買主側にそれぞれ別の不動産仲介会社がつくもので、広く一般的な取引形態です。
例えば、売主はA社に売却を依頼し、買主はB社に物件探しを依頼しているケースを考えてみましょう。
B社がA社の物件を見つけて買主に紹介し、契約が成立した場合、A社は売主からのみ仲介手数料を受け取り、B社は買主からのみ仲介手数料を受け取ることになります。
1つの契約に対して、1社あたりの利益は片方の当事者から受け取る仲介手数料のみ。だから「片手」と呼ばれるのです。
両手取引
一方、両手取引とは1つの不動産仲介会社が、売主と買主の両方の仲介を行います。
A社が売却依頼を受けた物件を、自社で見つけてきた買主に紹介して契約が成立した場合を考えてみてください。
A社は売主と買主の双方から仲介手数料を受け取ることができますよね。つまり、仲介会社の利益は片手取引の2倍になるのです。このことから「両手」と呼ばれます。
両手取引は、売主と買主の情報伝達がスムーズにできて、取引がスピーディーに進みやすいメリットがあります。
しかしその反面、「利益相反」のリスクがあります。
例えば、仲介会社が両手取引を成立させたいがために、他の仲介会社からの購入希望者の紹介を断ったとしましょう。こうした行為は「囲い込み」と言われます。
囲い込みが行われると、売主はより良い条件で不動産を売却できる機会を失ってしまうかもしれません。買主も選択肢が狭められて不利益が生じます。
もちろん、多くの仲介会社は売主や買主の双方の利益を考え、誠実に業務を行っています。
しかしながら、このような取引形態があることも事実であり、不動産仲介会社の利益構造に大きく関わっていることは知っておくとよいと思います。
仲介手数料以外の利益は?
不動産仲介会社の主な利益は仲介手数料ですが、それ以外にも以下に挙げたような収益源が存在します。とはいえ、これらは本来の仲介業務とは別のサービスとなり、会社によって発生しない場合もあります。
広告料やコンサルティング料
一般的なチラシやWeb掲載といった売却活動にかかる広告費は、仲介手数料に含まれています。
しかし、例えば遠方のニーズ調査や特殊な広告など、売主から特別な依頼があった場合、事前の承諾を得た上で、その実費や手数料が請求されることがあります。
関連業者からの紹介料(バックマージン)
不動産取引には、司法書士(登記手続き)、土地家屋調査士(測量)、リフォーム会社、引越し業者、火災保険代理店、金融機関など、さまざまな専門家や業者が関わります。
不動産仲介会社がこれらの業者にお客様に紹介し、成約に至った場合、紹介料を受け取っていることがあります。これも仲介会社の収益の一部となり得るものです。
まとめ
不動産仲介会社の利益について、疑問や不安は解消されたでしょうか。
利益の柱となる仲介手数料は、法律で上限額が定められている上に、不動産取引を円滑に進めるために必要なさまざまなプロセスに対する正当な対価です。
これから不動産の売買を検討される方は、こうした利益の構造を少しでも理解しておくと、提示された手数料に納得しやすくなると思います。
また「これはおかしいのではないか?」といったことにも気づきやすくなるでしょう。
そして何より、大切な資産を売買する不動産取引では、信頼できる不動産仲介会社を見つけることが非常に重要です。業社選びにおいても、今回の解説をぜひ参考にしていただけたらと思います。
参考:国交相ホームページhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html