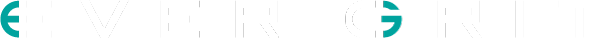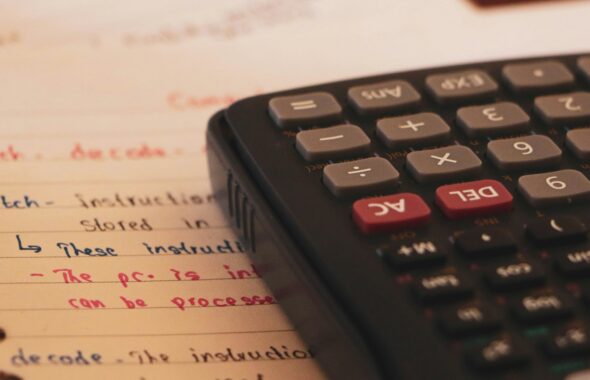投資信託の利回りとは?
投資信託の利回りとは、一般的に1年間の投資の元本金額に対して得られた利益の割合を指します。利回りは投資信託選びの重要なポイントとなりますが、注意すべき点もあります。
今回は、投資信託の利回りについてわかりやすく解説します。
1.あらためて投資信託とは?
まずは、投資信託についておさらいしましょう。
投資信託とは、1つの商品(ファンド)にさまざまな投資先が組み込まれている金融商品で、証券会社や銀行などで購入できます。例えば国内外の株式に投資するもの、不動産や金に同士するものなど、ファンドの種類は大変豊富で、金融機関によって取り扱っているラインアップは異なります。
投資信託を購入するために投資家が支払ったお金は、1つにまとめられて信託銀行が保管します。その大きな資金を使って、ファンドに組み込まれた投資先の「どれにどのくらい投資するか」はファンドを作った投資信託運用会社が考えて信託銀行に指図します。
このように投資信託は、ファンドを販売する金融機関、投資家から集めたお金を管理する信託銀行、ファンドの中身の運用の指図をする投資信託運用会社がそれぞれの役割を担いながら運用を進めていくのが特徴です。
投資信託で得られる利益は以下の2つです。
・分配金(インカムゲイン)
投資信託運用会社の運用によって得られた利益から、決算ごとに投資家に配当される利益。運用成績によって金額が変わり、支払われない場合もあります。
・譲渡益(キャピタルゲイン)
投資信託を売却することで得られる利益。投資信託に組み込まれている株や債券などはつねに価格が変動しています。それらの動きを基に、投資信託の価格(基準価額)は1日に1回算出、公表されます。投資信託を売却する際、購入時より高い価格で売れた場合に得られる差益が譲渡益です。
ファンドに組み込まれた資産の運用は投資のプロである運用会社に任せられること、ファンドを購入することで個人では投資しにくい国や地域、資産にも投資できることは投資信託の大きな特徴です。またさまざまな投資先に分散して投資すること(分散投資)は、リスクの軽減にもつながります。
投資信託は一般的に1万円程度から購入できますが、金融機関によっては100円や1,000円から購入できるサービスもあります。少額からの積み立て投資ができるのもメリットといえるでしょう。
2.計算方法も紹介! 投資信託の利回りとは?
投資信託の利回りとは、最初に投資した購入価格に対する分配金や譲渡益といった利益の割合であり、「%(パーセント)」で示されます。以下の計算式で算出することができます。
<投資信託の利回り(%)=収益(分配金+譲渡益)÷運用年数÷投資金額×100>
例えば、100万円で投資信託を購入したとしましょう。10年間運用してトータル10万円の分配金を受け取り、130万円で売却できた場合の利回りは以下の計算式で求められます。
<(10万円+30万円)÷10年÷100万円×100=+4%の利回り>
※手数料(販売手数料、信託報酬、信託財産留保額など)、税金は考慮していません
投資金額100万円に対して利回り4%とは、平均して年間4万円の収益が得られたことを意味します。
ただしこの利回りは、あくまでも一定期間における「過去の運用実績」により算出されたものです。実際の利回りは基準価格の動きや、運用年数としてどの期間を切り取るかによって変わってくることに注意しましょう。つまり、同じファンドであってもいつ購入していつ売るかによって利回りは違ってくるのです。
投資信託の各商品の利回りは、金融機関のホームページの商品一覧などで見ることができます。1年の利回りのほか直近3か月など短期間の利回りも掲載されている場合がありますので、参考にしてみてください。
また、投資信託は元本が保証されていません。運用成績によって、利回りはマイナスになることもありますし、元本割れのリスクがあることも必ず知っておきましょう。
3.投資信託選びでは利回り以外にも注目!
利回りは商品選びの重要なポイントにはなりますが、利回りが高いからといって必ずたくさんの利益を得られる商品というわけでもありません。あくまで過去の実績なので、「自分は●%くらいの利回りで資産を運用したい」といった希望と照らし合わせる、参考情報と捉えるのがよいでしょう。
投資の世界では「ハイリスク・ハイリターン」が基本です。利回りが高いファンドは、大きく値上がりする可能性が期待できる分、大きく値下がりするリスクも含んでいます。自分が理想とする利回りに加えて、自分がどれくらいのリスクなら許容できるのかも考えながら、商品を選ぶことが大切です。
投資信託の商品ページには、利回りの他にもさまざまな情報が表示されています。例えば「騰落率(とうらくりつ)」は、基準価額が一定期間にどのくらい変動したかを%で示したものです。騰落率の推移はさまざまな期間で算出されているので、短期だけでなく長期の推移も参考にしましょう。
また投資信託を選ぶ上では、コストも軽視できません。金融機関や商品によって異なりますが、投資信託を購入、保有、売却する際には以下の費用がかかります。中でも信託報酬は、ファンド内の資産の運用や管理を任せるための手数料で、投資信託ならではのコストです。
・購入時手数料
・信託報酬(運用管理費用)
・監査報酬
・売買委託手数料
・信託財産留保額 など
運用で利益が出ても、コストが大きければ手元に入る利益は減ってしまいます。購入前には必ず各手数料について確認しましょう。
投資信託の運用で得た利益には、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税(2037年12月31日まで)0.315%)の税金がかかります。新NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)を活用すれば、一定の投資額まで税金が非課税となります。
4.まとめ
今回は、投資信託の利回りについて解説しました。
よく使われる言葉ですが、「利率」や「利息」などと混同されることも多いので注意しましょう。
インターネット上には金融庁の「つみたてシミュレーター」など、利回り、毎月の投資額、投資する期間などを設定すると、将来どれくらい資産が増えていくのか計算できるシミュレーターがあります。理想とする利回りを考える際に役立ちますので、ぜひ使ってみてください。
自分が許容できるリスク、自分に合った投資方法にお悩みの場合は、資産運用のプロに相談するのも一案です。弊社でもお手伝いができますので、お気軽にご相談ください。
参考:
金融庁ホームページ
(https://www.shiruporuto.jp/public/)
(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/tsumitate-simulator/)
一般社団法人 投資信託協会ホームページ